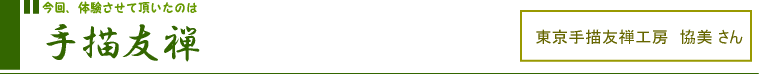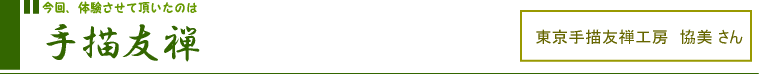|
|
■今回、訪問させて頂いたのは
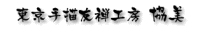 |
| |
|
|
| 訪問先 |
|
東京手描友禅工房 協美 さん |
| 講師 |
|
大澤 敏 さん、大澤 学 さん |
|
|
|
|
|
詳細は>> |
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
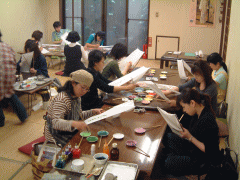 |
|
| ■ |
|
着物の世界の中で色彩を自由に使うことのできる技法、友禅。華やかにも自由に創作でき、女性を艶やか鮮やかに、綺麗にみせることができるのが特徴といいます。 |
|
|
|
| ■ |
|
今回体験させていただいた東京手描き友禅さんは下落合の閑静な住宅街の中にある工房です。この地に開いて25年、現役の職人の方が教室を設けていることは珍しいそうです。 |
|
|
|
| ■ |
|
大澤学さんがこの世界に入ったのは、父・大澤敏さん(東京都認定伝統工芸士)が手描友禅の職人であったことも一つのきっかけと言います。子供の頃には特にこの世界に進もうとは思っていなかったそうですが、学校を卒業した当時、工房では敏さんもお弟子さん方も忙しく動き回る日々。配送などを手伝っているうちに、友禅の修行の道に入られていたのだとか。 |
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| ■ |
|
今回は、通常のお教室で体験参加させていただきました。木洩れ日の落ちる、半地下の畳敷きの工房に、座卓が並びます。敏さん、壁際には、火鉢が。冬には凍える手を翳し暖をとり、また作品を乾かしたりにも使うそうです。 |
|
|
|
| ■ |
|
数ある工程の中で、半襟染めの工程を体験。半襟の生地は絹製で、先生が手描きで事前に絵柄を作製しているものだそうです。数種類の絵柄から一つを選んで着色開始。7種類くらいある原色から混ぜ合わせながら自分のイメージする色を調合していきます。配色を思案したり色を合わせたりと、時間が経つのを忘れます。ただ、「塗り絵と同じような感じだけど難しいよ」と言われたとおり、正直難しいです。「こうしよう」と筆を持って、十数秒後には後悔すること度々。でも、そこから「挽回」していくのもまた、いいですね。生地に筆をひとつひとつ丁寧に”置いて”いく作業に没頭していると、掛時計のカチカチという音だけがこの心静かな世界に響いているのに気がつきます。こうして、時計の音に耳を澄ませるのも何年ぶりでしょうか。 |
|
|
|
| ■ |
|
合間には奥さま(着付けの先生をされています)がお茶を入れてくださり、皆さん手を休めて卓袱台を囲んでの談笑。とても、アットホームな雰囲気です。この日いらしていた生徒さんは、自分で着るための着物を一から作ってらっしゃるとのことでした。外国の方も体験にいらっしゃるそうです。言葉は通じなくてもちゃんとできるんだそうです、ものづくりは言葉の壁を超越します。 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| ■ |
|
出来あがるまでに時間がかかってしまいました(5時間も!通常は2、3時間という話でした・・・)が、「できるまで帰れませんよ(笑)」と仰っていただく次第(お気遣いに感謝です)で、仕上がるまで”しっかり”体験させていただきました。※描きあげた生地は、蒸し、水洗、湯のしなどといった処理を施した後に、郵送してくださいます。 |
|
|
|
| ■ |
|
敏さんが合間合間に友禅の世界の話から日常のちょっとした面白話まで、きさくに話をふりまいてくれます。大澤さん親子の職人道のお話には心うたれます。石の上にも3年、体験終了後も、ものづくりのお話やお仕事のお話をさせて頂いていたら、ついつい長居をしてしまいました。 |
|
|
|
| ■ |
|
体験は「ハンカチなどの物でもいいのだろうけれど、やはり本格的に体験して頂きたい。着物に関係するもので実際に使えるものを」という思いで、半襟の作製をメニューにされているそうです。やはり何ヶ月もかけて作るものは見た目も質も持ちも違うことを体感できました。ありがとうございました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|